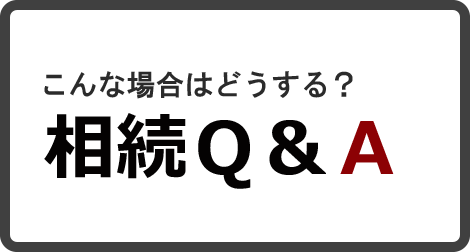こんな場合はどうする?相続Q&A
法定相続人に関すること
行方不明者を除外してなされた遺産分割協議は無効となります。そこで、共同相続人の中に行方不明の者がいる場合には、その生死不明期間に応じて失踪宣告の申立、あるいは不在者財産管理人の選任申立を行う必要があります。
生死が7年以上不明な場合
利害関係人(失踪者の配偶者・法定相続人など)は家庭裁判所に対して、その者の失踪宣告を申し立てることができます(失踪宣告の申立についてはこちら)。失踪宣告がなされると生死不明となった時点から7年間の期間満了を待って死亡したものとみなされます。被相続人よりも前に、失踪者が死亡した者とみなされれば、その者に子などがいる場合には、その子が失踪者を代襲して相続人となりますので、この代襲相続人を加えて遺産分割協議を行うことになります。
生死不明期間が7年に満たない場合
生死不明期間が7年に満たない場合やどこかで生存しているとの噂がある場合などは、利害関係のある共同相続人が家庭裁判所に対し不在者の財産管理人の選任を請求することになり、ここで選任された財産管理人が不在者に代わって遺産分割協議に参加します(不在者の財産管理人の選任申立についてはこちら)。なお、財産管理人には処分権限がありませんので、分割協議を成立させるにあたり家庭裁判所の許可を得る必要があります。
生死が7年以上不明な場合
利害関係人(失踪者の配偶者・法定相続人など)は家庭裁判所に対して、その者の失踪宣告を申し立てることができます(失踪宣告の申立についてはこちら)。失踪宣告がなされると生死不明となった時点から7年間の期間満了を待って死亡したものとみなされます。被相続人よりも前に、失踪者が死亡した者とみなされれば、その者に子などがいる場合には、その子が失踪者を代襲して相続人となりますので、この代襲相続人を加えて遺産分割協議を行うことになります。
生死不明期間が7年に満たない場合
生死不明期間が7年に満たない場合やどこかで生存しているとの噂がある場合などは、利害関係のある共同相続人が家庭裁判所に対し不在者の財産管理人の選任を請求することになり、ここで選任された財産管理人が不在者に代わって遺産分割協議に参加します(不在者の財産管理人の選任申立についてはこちら)。なお、財産管理人には処分権限がありませんので、分割協議を成立させるにあたり家庭裁判所の許可を得る必要があります。
未成年者が法律行為をするには、法定代理人(通常は親権者)の同意が必要です。
しかし、相続において被相続人の配偶者と子は共に利害が対立する関係にあります。そのため親権者が未成年の子を代理して遺産分割協議を行うことは利益相反行為として許されず、子のために特別代理人を選任するよう家庭裁判所へ申立てなければなりません。
特別代理人選任の申立についてはこちら
未成年の子が複数いる場合は、それぞれにつき特別代理人を選任する必要があり、また子が相続放棄する場合であっても、特別代理人の選任を要します。
なお、親が相続放棄をしていれば、未成年の子の代理人として遺産分割協議に参加することはできますが、この場合であっても、複数の子を代理することはできず、子一人だけを代理し、その他の子については特別代理人の選任を申立てなければなりません。
しかし、相続において被相続人の配偶者と子は共に利害が対立する関係にあります。そのため親権者が未成年の子を代理して遺産分割協議を行うことは利益相反行為として許されず、子のために特別代理人を選任するよう家庭裁判所へ申立てなければなりません。
特別代理人選任の申立についてはこちら
未成年の子が複数いる場合は、それぞれにつき特別代理人を選任する必要があり、また子が相続放棄する場合であっても、特別代理人の選任を要します。
なお、親が相続放棄をしていれば、未成年の子の代理人として遺産分割協議に参加することはできますが、この場合であっても、複数の子を代理することはできず、子一人だけを代理し、その他の子については特別代理人の選任を申立てなければなりません。
相続人の中に、認知症や知的障がい、精神障がい等により、自分の行為や、その行為の結果がどのような意味を持つのか判断できない人がいる場合、家庭裁判所に後見開始の審判を申立てて、成年後見人を選任してもらい、その成年後見人と遺産分割協議をする必要があります。
成年後見人の選任についてはこちら
この後見には、保護が必要な程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの制度があり、判断能力が残存する「保佐」「補助」の場合に保佐人や補助人が遺産分割を代理するには、保佐・補助開始の審判とは別に遺産分割の代理権を付与する旨の審判が必要となります。
また、被補助人本人が遺産分割に参加する場合は、補助人の同意が必要となることから、補助開始の審判とは別に補助人に同意権を付与する旨の審判を受ける必要があります。
成年後見人の選任についてはこちら
この後見には、保護が必要な程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの制度があり、判断能力が残存する「保佐」「補助」の場合に保佐人や補助人が遺産分割を代理するには、保佐・補助開始の審判とは別に遺産分割の代理権を付与する旨の審判が必要となります。
また、被補助人本人が遺産分割に参加する場合は、補助人の同意が必要となることから、補助開始の審判とは別に補助人に同意権を付与する旨の審判を受ける必要があります。
相続において胎児は既に生まれたものとみなされますので、胎児を除外した遺産分割協議は無効と解されます。そのため、胎児の出生を待って特別代理人選任の申立を行い、その代理人と遺産分割協議をするのが無難といえます。なお、緊急を要する場合は、遺産分割審判の申立をすることも可能です。
遠方などの事情により遺産分割協議に参加できない場合には、相続人の誰かが作成した遺産分割案を郵送し、持回り方式で遺産分割協議に代えることが認められています。持ち回りで受け取った遺産分割協議書には署名捺印し、印鑑証明書を添付しなければなりません。
しかし、海外在住のため日本に住所がなく、印鑑証明書の交付を受けられない場合には、印鑑証明に代えてサイン証明(署名(および拇印)証明書)を添付すればよいとされています。
サイン証明とは、日本に住民登録をしていない海外在住者に対し、日本の印鑑証明書に代わるものとして日本での手続きのために発給されるもので、申請者の署名(および拇印)が確かに領事の面前で証明されたことを証明するものです。
交付を受けるための具体的な手続きとしては、遺産分割協議書を住んでいる国の日本大使館あるいは総領事館に持参して、領事の面前で署名および拇印を捺印し、遺産分割協議書と署名(および拇印)証明書を綴り合せて割り印をします。
これを日本へ返送すれば、この遺産分割協議書で相続登記等の申請が可能となります。
しかし、海外在住のため日本に住所がなく、印鑑証明書の交付を受けられない場合には、印鑑証明に代えてサイン証明(署名(および拇印)証明書)を添付すればよいとされています。
サイン証明とは、日本に住民登録をしていない海外在住者に対し、日本の印鑑証明書に代わるものとして日本での手続きのために発給されるもので、申請者の署名(および拇印)が確かに領事の面前で証明されたことを証明するものです。
交付を受けるための具体的な手続きとしては、遺産分割協議書を住んでいる国の日本大使館あるいは総領事館に持参して、領事の面前で署名および拇印を捺印し、遺産分割協議書と署名(および拇印)証明書を綴り合せて割り印をします。
これを日本へ返送すれば、この遺産分割協議書で相続登記等の申請が可能となります。
遺贈とは、被相続人が遺言で財産を贈与することをいい、包括遺贈と特定遺贈の2種類があります。
包括遺贈とは「遺産の半分」や「遺産の○分の1」といったように具体的に財産を特定せず全財産の一定割合を指定し包括的に行う遺贈のことで、他方、特定遺贈とは「この土地」というように具体的に財産を特定して行う遺贈のことをいいます。
包括遺贈の場合は、その受遺者は相続人と同一の権利義務を有することになりますので、遺産分割協議に参加して、受贈する財産について話し合いで決定することになります。
包括遺贈とは「遺産の半分」や「遺産の○分の1」といったように具体的に財産を特定せず全財産の一定割合を指定し包括的に行う遺贈のことで、他方、特定遺贈とは「この土地」というように具体的に財産を特定して行う遺贈のことをいいます。
包括遺贈の場合は、その受遺者は相続人と同一の権利義務を有することになりますので、遺産分割協議に参加して、受贈する財産について話し合いで決定することになります。
相続分の譲渡は、遺産全体に対して各共同相続人が有する包括的持分ないし法律上の地位の移転をいうと解されていますので、相続分を譲り受けた者は、遺産分割協議が成立するまでの間、共同相続人と同様、相続財産を管理し遺産分割を請求し、またはこれに参加する権利を取得することになります。したがって遺産分割の協議に際し、相続分を譲り受けた第三者を参加させる必要があります。
しかし、相続人の中には、見ず知らずの第三者を加えて遺産分割協議をすることに抵抗を感じられる方もいらっしゃるかと思います。そこで、法は他の共同相続人に、第三者に譲渡された相続分の取戻権を認めています。 この取戻権は、譲渡から一か月以内に行使する必要があり、その方法としては、譲受人に対する一方的な意思表示で足り譲受人の承諾は要しませんが、譲受人に対し、行使時の相続分の評価額および費用を償還する必要があります。
では、こうして取戻した相続分は誰に帰属することになるのでしょうか。この点については争いがあり、相続人全員に帰属するとの説もありますが、共同相続人のうち一人が単独で行使した場合はその者に独占的に帰属し、共同して行使した場合は、償還した価格および費用の割合に応じて各相続人に帰属すると解するのがベターかと思われます。
しかし、相続人の中には、見ず知らずの第三者を加えて遺産分割協議をすることに抵抗を感じられる方もいらっしゃるかと思います。そこで、法は他の共同相続人に、第三者に譲渡された相続分の取戻権を認めています。 この取戻権は、譲渡から一か月以内に行使する必要があり、その方法としては、譲受人に対する一方的な意思表示で足り譲受人の承諾は要しませんが、譲受人に対し、行使時の相続分の評価額および費用を償還する必要があります。
では、こうして取戻した相続分は誰に帰属することになるのでしょうか。この点については争いがあり、相続人全員に帰属するとの説もありますが、共同相続人のうち一人が単独で行使した場合はその者に独占的に帰属し、共同して行使した場合は、償還した価格および費用の割合に応じて各相続人に帰属すると解するのがベターかと思われます。
死後認知の訴えを提起している者がいる場合には、仮に認知が認められてその者が相続人になったとしても、既に成立した遺産分割協議は無効とはならず、他の共同相続人は認知によって相続人になった者に対して、その相続分に見合った金銭を支払えばよいとされています。したがって、認知の訴えを提起している者を除外して遺産分割協議を進めることに問題はありません。
法律上の婚姻関係がないため、内縁の配偶者には相続権はありませんが、子については、認知がされていれば、財産を相続することができます。
この点、婚姻関係にない男女の間で生まれた子は非嫡出子として、その相続分は、民法上、婚姻関係にある男女の間で生まれた子(嫡出子)の1/2とされてきましたが、平成25年9月の最高裁決定により、かかる民法の規定は、日本国憲法が保障する法の下の平等に反し不合理な差別を規定したものとして違憲とされ、これを受け同年12月の民法改正により、削除されました。したがって、婚外子であっても認知がなされていれば、その相続分は原則嫡出子と同じということになります。
この点、婚姻関係にない男女の間で生まれた子は非嫡出子として、その相続分は、民法上、婚姻関係にある男女の間で生まれた子(嫡出子)の1/2とされてきましたが、平成25年9月の最高裁決定により、かかる民法の規定は、日本国憲法が保障する法の下の平等に反し不合理な差別を規定したものとして違憲とされ、これを受け同年12月の民法改正により、削除されました。したがって、婚外子であっても認知がなされていれば、その相続分は原則嫡出子と同じということになります。
兄弟姉妹が相続人となる場合、父母を同じくする兄弟姉妹と、異父・異母兄弟姉妹とでは法定相続分が異なります。
異父・異母兄弟姉妹の相続分は、父母を同じくする兄弟姉妹のそれの半分となります。
異父・異母兄弟姉妹の相続分は、父母を同じくする兄弟姉妹のそれの半分となります。
法律上、嫡出子も養子も、子であることに変わりはく、原則通り同順位で、等分に相続します。なお、養子は実親との間にも親子関係があり、また親族関係も継続していますので、実親の相続、および兄弟姉妹の相続についても相続権を失いません。一方、特別養子の場合は養子縁組の成立により実親・親族との関係は終了しますので、これらの者との間で相続関係は発生しません。
【特別養子】原則として6歳未満の子どもの福祉のため特に必要があるときに、子どもとその実親側との法律上(戸籍上)の親族関係を消滅させ、実親子関係に準じる安定した養親子関係を家庭裁判所が成立させる縁組制度のこと。
【特別養子】原則として6歳未満の子どもの福祉のため特に必要があるときに、子どもとその実親側との法律上(戸籍上)の親族関係を消滅させ、実親子関係に準じる安定した養親子関係を家庭裁判所が成立させる縁組制度のこと。
配偶者であれば常に相続人になりますが、離婚すると戸籍も別になり、赤の他人となります。そのため、前妻は相続人とはなりません。もっとも、夫婦との間に子があれば、その後離婚しても、子との間の血族関係までは切れるわけではありませんので、前妻の子は相続人となります。
では後妻の連れ子に相続権は認められるでしょうか。まず、後妻は被相続人の配偶者として常に相続人となります。一方、後妻の連れ子との間には、血族関係がありませんので、再婚に際し、被相続人と養子縁組をしていない限り、相続権は認められません。
では後妻の連れ子に相続権は認められるでしょうか。まず、後妻は被相続人の配偶者として常に相続人となります。一方、後妻の連れ子との間には、血族関係がありませんので、再婚に際し、被相続人と養子縁組をしていない限り、相続権は認められません。
本来は相続人になるべき者であっても一定の事情があったり、あるいは被相続人の意思で相続権を剥奪された場合には、相続人になれなくなります。
相続人の相続資格を剥奪する制度には、①一定の事由があれば当然に相続資格を喪失する相続欠格、および②被相続人の意思により相続権を剥奪する相続人廃除があります。
詳細はこちら
相続人の相続資格を剥奪する制度には、①一定の事由があれば当然に相続資格を喪失する相続欠格、および②被相続人の意思により相続権を剥奪する相続人廃除があります。
詳細はこちら
夫と子ども、どちらが先に死亡したかわからない場合、同時に死亡したものと推定され、互いに相続人とはならないことになります。例えば、夫Aさんと子Cさんが同時に死亡した場合、Aさんには妻Bさん、子Cさん、Dさんが、Cさんには妻Eさんがいたとして、Aさんの財産についてはBさんが1/2、Dさんが1/2を相続し、Cさんの財産についてはEさんが2/3、Bさんが1/3を相続することになります。
相続財産に関すること
遺言書があれば、財産はそれに従って処理されます。遺言書がない場合は、家庭裁判所で相続財産管理人が選任され、財産の処分を行います。相続財産管理人は相続人捜索のための官報公告と、債権の申出の公告を行い、公告期間内に相続人が現れない場合は、債権債務を清算します。負債を清算してもなお遺産が残っている場合には、特別縁故者として申し出る者があれば、審判により財産が分与されることがあります。これらの一連の手続きを経て、なお財産が残っている場合は国庫に納められることになります。
相続財産である賃貸マンションの家賃や、預金の利息、または株式の配当金など遺産から生ずる収益は、遺産分割協議の対象となるのでしょうか。
この点、判例は、「遺産は、相続人が複数いるときは、相続開始から遺産分割までの間、相続人全員の共有の状態にあるのだから、その間に発生した賃料債権は遺産とは別個の財産というべきであって、各相続人がその相続分に応じてそれぞれ単独で取得するものであり、後にされた遺産分割の影響を受けない」と判断しています。
従って、相続開始から遺産分割までの間に家賃などの遺産から生じた収益は、遺産分割協議の対象とはならず、各相続人がその相続分に応じて取得することになります。
この点、判例は、「遺産は、相続人が複数いるときは、相続開始から遺産分割までの間、相続人全員の共有の状態にあるのだから、その間に発生した賃料債権は遺産とは別個の財産というべきであって、各相続人がその相続分に応じてそれぞれ単独で取得するものであり、後にされた遺産分割の影響を受けない」と判断しています。
従って、相続開始から遺産分割までの間に家賃などの遺産から生じた収益は、遺産分割協議の対象とはならず、各相続人がその相続分に応じて取得することになります。
相続財産は、遺産分割協議が完了するまで共同相続人全員の共有に属すると考えられ、そのうちの一人が勝手に処分することは許されません。以下、遺産の種類に応じて説明します。
相続人が配偶者Bと子C,Dの3人である場合においてCが無断で下記相続財産を第三者に売却したとします。
①処分された遺産が不動産の場合:Cは法定相続分の1/4以外の3/4については全くの無権利者であるため、たとえ譲り受けた第三者が登記を信頼して移転登記を受けた場合であっても、他の相続人は3/4の持ち分について登記の抹消を請求することができます。
②処分された遺産が動産の場合:動産は不動産とは異なり、たとえ無権利者からの譲渡であっても譲受人が譲渡人の所有権を善意無過失に信頼して譲り受けた場合には所有権を取得することができます。これを善意取得ないしは即時取得といいます。本件でも第三者がCの所有権を善意無過失に信頼して譲り受けたとすれば、第三者が所有権を善意取得し、他の相続人はその返還を請求できなくなります。
相続人が配偶者Bと子C,Dの3人である場合においてCが無断で下記相続財産を第三者に売却したとします。
①処分された遺産が不動産の場合:Cは法定相続分の1/4以外の3/4については全くの無権利者であるため、たとえ譲り受けた第三者が登記を信頼して移転登記を受けた場合であっても、他の相続人は3/4の持ち分について登記の抹消を請求することができます。
②処分された遺産が動産の場合:動産は不動産とは異なり、たとえ無権利者からの譲渡であっても譲受人が譲渡人の所有権を善意無過失に信頼して譲り受けた場合には所有権を取得することができます。これを善意取得ないしは即時取得といいます。本件でも第三者がCの所有権を善意無過失に信頼して譲り受けたとすれば、第三者が所有権を善意取得し、他の相続人はその返還を請求できなくなります。
遺産分割に関すること
相続財産は不動産や預貯金などのプラス財産だけでなく、借金や保証債務などのマイナス財産も含まれます もっとも、遺産分割の対象となるのはプラス財産だけで、マイナス財産である金銭債務などは、遺産分割を経ることなく相続分に応じて各共同相続人に承継されることになります。そのため、特定の者が債務を引き受けるような遺産分割協議が成立しても、それは相続人相互の間では有効ですが、債権者に主張することはできません。というのも、相続人に任意に債務負担の割合を決めることを認めれば、返済能力のない者に債務全額を引き受けさせるような事態も起こりかねず、債権者の権利が害されるからです。
ただし、法定相続分とは異なる割合で債務を負担することに債権者が承諾すれば、債権者との間でも有効に成立しますので、この場合には、債務を引き受けない他の相続人は債権者との間で免責的債務引受契約証書を作成しておくようにします。
ただし、法定相続分とは異なる割合で債務を負担することに債権者が承諾すれば、債権者との間でも有効に成立しますので、この場合には、債務を引き受けない他の相続人は債権者との間で免責的債務引受契約証書を作成しておくようにします。
相続財産が自宅不動産のみの場合の分割方法としては①換価分割、②代償分割が考えられます。いずれの方法を選択するかは、遺産分割後、共同相続人の誰かが当該不動産に居住するつもりがあるか否かで決定されます。
例えば、被相続人が一人暮らしであった場合で、相続人の誰も、居住の意思がない場合には、当該不動産を売却して、それにより得た金銭を法定相続分に応じて分配する換価分割という方法をとることになります。これに対し、相続人の誰かが、当該不動産に居住する意思がある場合や、相続開始前から被相続人と同居し、以後も居住する意思がある場合には、その者が当該不動産を取得し、それと引き換えに他の相続人には代償金を支払う代償分割によることになります。しかし、代償分割を行うには、ある程度の資力が必要となりますので、居住する意思はあるが代償金を支払う資力がない場合は換価分割によらざるを得なくなります。
換価分割や代償分割ではどうしても調整がつかないという場合には、分割をせずに共同相続のまま、すなわち共有状態にしておくということも考えられますが、数次相続が発生した場合に権利関係が複雑になったり、いざ売却しようにも共同相続人全員の合意が得られず売却できない、といった後のトラブル発生の原因ともなり得ますので、お勧めはしません(不動産共有化のリスク)。
なお、換価分割の場合、売却に先立ち、相続人全員で相続登記を経由する必要がありますが、共同相続人のうちの一人を代表者として相続登記を申請することも可能です。
例えば、被相続人が一人暮らしであった場合で、相続人の誰も、居住の意思がない場合には、当該不動産を売却して、それにより得た金銭を法定相続分に応じて分配する換価分割という方法をとることになります。これに対し、相続人の誰かが、当該不動産に居住する意思がある場合や、相続開始前から被相続人と同居し、以後も居住する意思がある場合には、その者が当該不動産を取得し、それと引き換えに他の相続人には代償金を支払う代償分割によることになります。しかし、代償分割を行うには、ある程度の資力が必要となりますので、居住する意思はあるが代償金を支払う資力がない場合は換価分割によらざるを得なくなります。
換価分割や代償分割ではどうしても調整がつかないという場合には、分割をせずに共同相続のまま、すなわち共有状態にしておくということも考えられますが、数次相続が発生した場合に権利関係が複雑になったり、いざ売却しようにも共同相続人全員の合意が得られず売却できない、といった後のトラブル発生の原因ともなり得ますので、お勧めはしません(不動産共有化のリスク)。
なお、換価分割の場合、売却に先立ち、相続人全員で相続登記を経由する必要がありますが、共同相続人のうちの一人を代表者として相続登記を申請することも可能です。
既に成立した遺産分割協議が無効かどうかは新たに発見された財産によって異なります。原則としては、新たに発見された遺産についてのみ共同相続人間で協議をすれば足り、遺産分割協議をやり直す必要はありません。もっとも、発見された遺産が重要なもので、相続人がその遺産の存在を知っていたならば当初のとおり遺産分割協議を行わなかったと認められる場合は、錯誤を理由として無効となると解されます。従って、この場合には遺分割協議をやり直さなければなりません。
相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合や、協議に応じようとしない相続人がいる場合には、家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てることになります。
遺産分割調停は、裁判官と調停委員から構成される調停委員会によって進められ、各相続人から事情を聞いたり、場合によっては妥当な解決策を示して紛争解決へ向けて家庭裁判所が関与するものの、最終的には相続人全員の話し合いによる合意が解決内容となります。この意味で、遺産分割調停は、裁判所という公的な第三者機関を介した話し合いと言えます。相続人全員の合意が成立した場合は、調停調書が作成されます。この調書には確定判決と同一の効力がありますので、これに基づいて調停の内容を強制的に実現することが可能となります。
他方、合意が成立しなかった場合は、自動的に審判手続きへ移行することになります。
遺産分割調停は、裁判官と調停委員から構成される調停委員会によって進められ、各相続人から事情を聞いたり、場合によっては妥当な解決策を示して紛争解決へ向けて家庭裁判所が関与するものの、最終的には相続人全員の話し合いによる合意が解決内容となります。この意味で、遺産分割調停は、裁判所という公的な第三者機関を介した話し合いと言えます。相続人全員の合意が成立した場合は、調停調書が作成されます。この調書には確定判決と同一の効力がありますので、これに基づいて調停の内容を強制的に実現することが可能となります。
他方、合意が成立しなかった場合は、自動的に審判手続きへ移行することになります。
相続放棄に関すること
法定相続人には第1順位(子)、第2順位(親)、第3順位(兄弟姉妹)という優先順位があります。 子の一人が相続放棄をした場合、その者を省いた第1順位の相続人と配偶者で遺産分割協議をすることになります。他に子がいない場合は、次順位の親に相続権が移り、それもいない場合は兄弟姉妹に移ります。被相続人に多額の借金があることを理由に相続放棄をする場合には、他の相続人が知らない間に多額の負債を押し付けられていた、ということがないよう、必ず次順位の相続人に連絡するようにしましょう。
相続人が相続財産の一部でも処分したときは、単純承認したもの(相続したもの)とみなされ、以後、相続放棄や限定承認をすることができなくなります。
単純承認とみなされる処分行為には、売買や譲渡などの法律行為だけでなく、家屋の取り壊しなどの毀損・破棄といった事実行為も含まれます。
もっとも、相続人が行った処分行為のすべてが単純承認とみなされるわけではなく、それが保存行為や短期賃貸借(土地であれば5年、建物であれば2年以内の期間の賃貸借契約)に当たる場合は単純承認とはみなされません。
詳しくはこちら
単純承認とみなされる処分行為には、売買や譲渡などの法律行為だけでなく、家屋の取り壊しなどの毀損・破棄といった事実行為も含まれます。
もっとも、相続人が行った処分行為のすべてが単純承認とみなされるわけではなく、それが保存行為や短期賃貸借(土地であれば5年、建物であれば2年以内の期間の賃貸借契約)に当たる場合は単純承認とはみなされません。
詳しくはこちら
相続人が相続放棄ないしは限定承認をする場合、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。ここに言う「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは通常相続人が被相続人の死亡の事実及びそれにより自己が相続人となったことを知った時を指し、原則、被相続人の死亡時がこれにあたるとされています。
しかし、熟慮期間経過後に負債が発覚した場合にまで、このような原則を貫くことは、被相続人に財産も負債も全くないと信じてこれを放置していた相続人に酷な場合もあります。そこで、判例は、例外的に「相続人が被相続人に相続財産が全くないと信じ、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において相続財産が全くないと信ずるについて相当な理由が認められるときは、相続人が財産の全部もしくは一部の財産の存在を認識した時または通常これを認識し得るべき時から起算するのが相当である」としています。したがって3ヶ月が経過している場合でも相続放棄が認められる場合がありますので、早急に専門家にご相談ください。
しかし、熟慮期間経過後に負債が発覚した場合にまで、このような原則を貫くことは、被相続人に財産も負債も全くないと信じてこれを放置していた相続人に酷な場合もあります。そこで、判例は、例外的に「相続人が被相続人に相続財産が全くないと信じ、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において相続財産が全くないと信ずるについて相当な理由が認められるときは、相続人が財産の全部もしくは一部の財産の存在を認識した時または通常これを認識し得るべき時から起算するのが相当である」としています。したがって3ヶ月が経過している場合でも相続放棄が認められる場合がありますので、早急に専門家にご相談ください。
相続財産が複雑・多額であるとか、各地に分散しているなどの場合には、3ヶ月の熟慮期間内で相続財産の調査を終了し、相続放棄をするか否かを判断することが難しいことがあります。このような場合は、家庭裁判所に対し、「相続の承認・放棄の期間伸長の申立」をすることができます。
未成年者が法律行為をするには、法定代理人(通常は親権者)の同意が必要ですが、相続において被相続人の配偶者と子は共に利害が対立する関係にあります。そのため親権者が、先行して又は同時に相続放棄をする場合を除き、未成年の子を代理して相続放棄をすることは利益相反行為として許されず、子のために特別代理人を選任するよう家庭裁判所へ申立なければなりません。
相続による借金を負担せずに自宅不動産を確保するには、相続人全員で限定承認を行い、先買権を行使する方法があります。先買権とは、限定承認を行った相続人に認められる権利で、家庭裁判所が選任した鑑定人による評価額を支払うことにより当該不動産を取得できるというも家庭裁判所に鑑定人の選任申立を行う必要があり、その鑑定人の費用(30万円程度)及び鑑定人の評価額を、先買権を行使する相続人の固有の財産から支払わなければなりません。また、当該不動産に抵当権等が設定されている場合には、先買権を行使しても、当然に抵当権に基づく競売を止めることは出来ず、別途抵当権者との合意が必要となります。
限定承認についてはこちら
限定承認についてはこちら